本記事では、ネットワークスペシャリスト試験(ネスペ)の令和6年度午後Ⅱ問1について、筆者の所感なども交えて解説していきます。
なお、画像や解答例は全てIPA(独立行政法人情報処理機構)から引用しております。
令和6年度春期 ネットワークスペシャリスト(NW)午後Ⅱ
令和6年度春期 ネットワークスペシャリスト(NW)午後Ⅱ 解答例
私は普段、左門至峰先生の「ネスペ」シリーズで学習を行っています。
午後Ⅰ・午後Ⅱのみにフォーカスを当て、とても丁寧に、そして詳細に解説されています。
より深い知識を求める方、ネットワークスペシャリスト試験を徹底的に対策したい方におすすめします。
本設問の概要について
大手EC事業を運営する、K社データセンターの拡張方針について問われた設問でした。
私自身聞き慣れない単語が頻出し、とても難しかったという印象でした。
ただ、問題文をしっかり読むことで、部分点狙いの解答ができたのではないかと思います。
簡単にですが用語の説明を記載しておきます。
全体像を掴んでいただくため、本設問のシナリオを掲載します。
- STEP.1導入部分
K社は大手EC事業を運営しており、EVPN(Ethernet VPN)を用いた拡張性の向上を検討しています。
現在はVXLAN(Virtual eXtensible Local Area Network)を利用していますが、ネットワークの拡張性向上のため、EVPN+VXLANの導入を目指し、技術検証を行っていくという流れです。 - STEP.2VXLANの概要
現状の構成で利用されているXVLAN、ならびにXVLANトンネルの端点であるVTEP(VXLAN Tunnel End Poin)について述べられています。
- STEP.3現行の検証ネットワーク
K社が構築している現行の検証ネットワークについての説明が書かれています。
構成図を中心に、経路制御や冗長構成について記述されています。
通信経路などが詳細に記載されているため、ここはしっかり理解しておきたいところです。 - STEP.4現行の検証NWにおけるVTEPの動作
現行の検証環境におけるVTEPの動作内容が記述されています。
- STEP.5EVPNの概要
導入部分でも記述した拡張性の向上を目指して、EVPNの導入を進めていきます。
本セクションではEVPNの概要として、大きく機能1〜3で説明がされています。
この機能1〜3は設問に対しかなりのヒントが散りばめられているため、しっかり理解しましょう。 - STEP.6新検証NWの設計
現行の検証NWを基に、EVPNを用いたVXLANを検証するためのネットワーク設計について進めていきます。
新環境でのネットワーク構成図が提示されています。(リンクアグリケーションを導入)
正直、聞き慣れない単語ばかりでかなり難しい設問になると思います。
誤りなどがありましたらぜひコメントなどでご指摘ください。
IPAの解答例について
| 設問 | 解答例 | 予想配点 | ||
|---|---|---|---|---|
| 設問1 | (1) | a | 24 | 3 |
| b | 3 | 3 | ||
| c | UDP | 3 | ||
| (2) | ① | イーサネットフレーム | 2 | |
| ② | VXLANヘッダー | 2 | ||
| ③ | IPv4ヘッダー | 2 | ||
| (3) | 同じレイヤー2のネットワークをもつ全てのリモートVTEPに転送するため | 7 | ||
| 設問2 | (1) | d | LSDB | 3 |
| e | 最短経路 | 3 | ||
| (2) | OSPFが動作する各L3SW | 5 | ||
| (3) | 複数ある経路のそれぞれの経路について、コストの合計値を同じ値にする。 | 7 | ||
| (4) | 一つの物理インタフェースに障害があっても、VTEPとして動作できるから | 7 | ||
| (5) | ア | × | 1 | |
| イ | × | 1 | ||
| ウ | × | 1 | ||
| エ | × | 1 | ||
| オ | ○ | 1 | ||
| カ | × | 1 | ||
| 設問3 | (1) | 239.0.0.1 | 2 | |
| (2) | VM11のMACアドレス、VNI及びL3SWのVTEPのIPアドレス | 5 | ||
| (3) | キ | 10010 | 2 | |
| ク | 10.0.0.31 | 2 | ||
| ケ | 10010 | 2 | ||
| コ | 10.0.0.11 | 2 | ||
| 設問4 | (1) | 利点 | iBGPビアの数を減らすことができる。 | 6 |
| 名称 | クラスターID | 3 | ||
| (2) | f | Unknown Unicast | 2 | |
| g | ESI | 2 | ||
| (3) | 二つの回線の帯域を有効に利用できる。 | 6 | ||
| (4) | MP-BGPを用いて学習する。 | 6 | ||
| (5) | VLAN IDに対応するVNIをもつ全てのリモートVTEP | 7 | ||
設問1
(1)
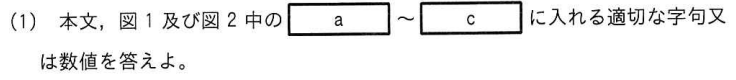
まずはお馴染みの穴埋め問題です。
(a),(b)
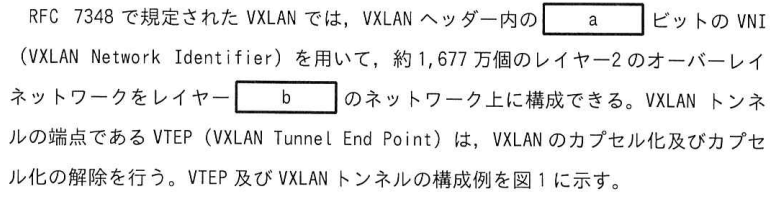
- (a)
VXLANヘッダーのVNIの個数について問われています。
すぐ後に「約1,677万個の〜ネットワーク上に構成できる」という記述がヒントです。
約1,677万個のネットワークを構成できるのは、2の24乗です。よって、正解は24ビットです。
- (b)
レイヤー2のオーバレイネットワークをどのレイヤー上に構成できるか問われています。
VXLANはレイヤー3のネットワーク上に構成することができます。
(a)24
(b)3
(c)
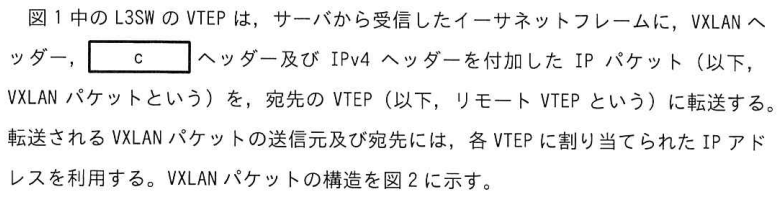
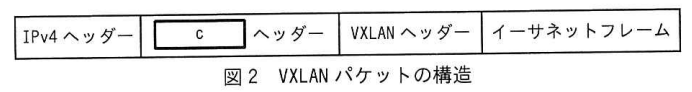
まずは図1を見てみましょう。
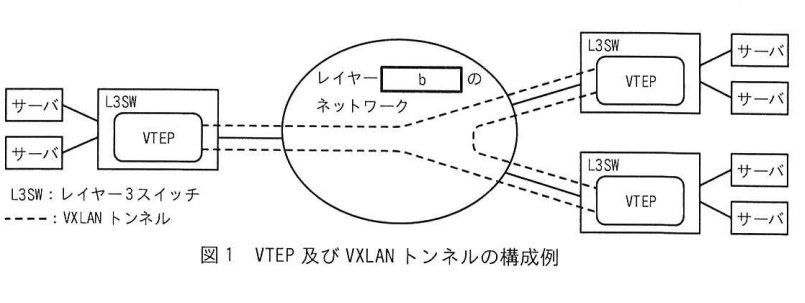
L3SW中のVTEPが、宛先であるリモートVTEPに転送する際に付加するヘッダーの名称について問われています。
ヒントは図2のパケット構造です。
IPv4ヘッダー(レイヤー3)より上位レイヤーであるため、トランスポート層(レイヤー4)のヘッダとなります。
XVLANはUDP(ポート4789)にてカプセル化されるため、UDPヘッダーが付与されます。
(c)UDP
(2)
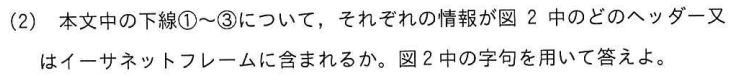
下線①〜③ならびに図2を見てみましょう。
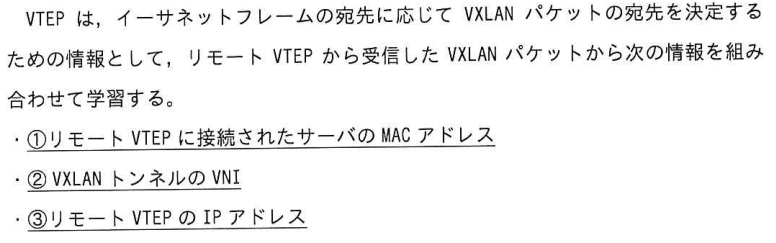
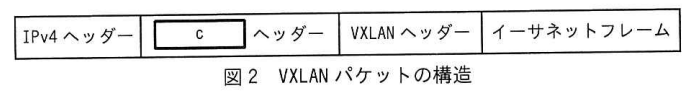
VTEPの動作として、リモートVTEPから受け取った下線①〜③の情報を組み合わせて宛先情報を学習します。
宛先にフレームを送出する際、学習した内容がどのヘッダーに含まれるかを問われています。
これは比較的簡単な問題だったと思います。
- リモートVTEPに接続されたサーバのMACアドレス(下線①)
「MACアドレス」と記載されているので、イーサネットフレームに含まれます。 - VXLANトンネルのVNI(下線②)
VXLANに含まれる情報のため、VXLANヘッダーに入ります。 - リモートVTEPのIPアドレス
IPアドレスのためIPv4ヘッダーに含まれます。
それぞれの正答は以下のとおりです。
①. イーサネットフレーム
②. VXLANヘッダー
③. IPv4ヘッダー
(3)
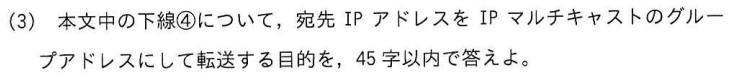
下線④を見てみましょう。
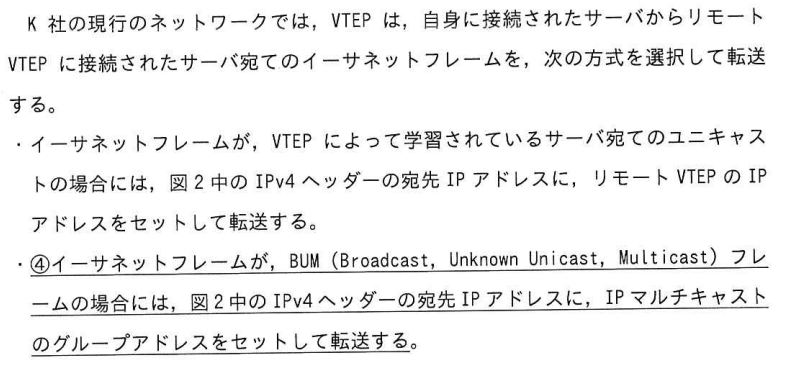
VTEPによって宛先が学習されていない場合、マルチキャストアドレスに転送する目的を問われています。
まずはBUM(Broadcast, Unknown Unicast, Multicast)の説明を記載します。
また、VXALN環境におけるBMUフレームの処理フローを記載します。
①. VTEPがマルチキャストグループを使用してBUMフレームを送信
②. 受信したVTEPはIGMPを利用してグループに参加
それでは設問に戻りましょう。
もしVTEPがこのBMUフレームをブロードキャストで転送すると、他のVTEPも含めた全ての端末にパケットを送信してしまいます。
これだとトラフィックに無駄が出てしまいます。
一方、VTEPがマルチキャストフレームで転送すると、マルチキャストのグループアドレスのみにパケットを送信します。
VM11がブロードキャストパケットを送信し、L3SW11のVTEPがマルチキャストパケットで転送した場合、図4の緑で囲った端末だけにパケットが送信されます。
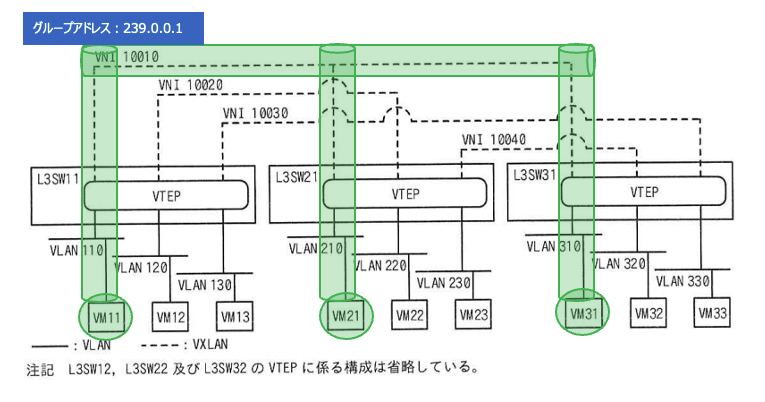
この設問ではマルチキャストにて転送する「目的」を問われています。
IPマルチキャストを利用する目的は、特定のVTEPに転送することです。
つまり、「同じレイヤー2のネットワークのVTEP」に転送することが目的です。
解答例は以下のとおりです。
同じレイヤー2のネットワークをもつ全てのリモートVTEPに転送するため(35字)
ちなみに私はブロードキャストと比較した内容で以下のように解答しました。
ブロードキャストと比較してトラフィックを抑えることができるため(31字)
的を得ているような得ていないような…
ただ、トラフィックについては設問中に言及されていないため、正解にはならなかったかもしれません。
設問2
設問2では、OSPFについての設問が多いです。
OSPFはネットワークスペシャリスト試験では頻出ジャンルのため、正解したいところですね。
(1)
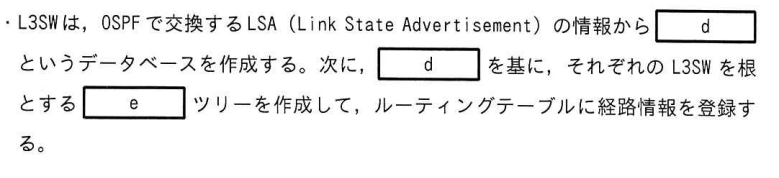
OSPFに関する穴埋め問題ですね。
(d)
OSPFではLSA(Link State Advertisement)という、リンクステート情報を伝達するメッセージを隣接ルータに送信します。
LSAを受信したルータは、LSDB(Link State Database)を作成します。
(e)
次に、作成したLSDBを基に、SPF(Shortest Path First/最短経路)ツリーを作成し、選出した経路をルーティングテーブルに登録します。
IPAの解答は「最短経路」ですが、「SPF」でも正解になったと思います。
(d)LSDB
(e)最短経路(SPF)
(2)
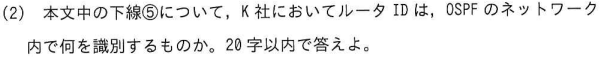
まずは下線⑤を見てみましょう。
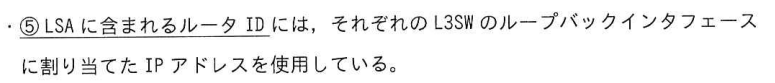
ルータIDはそのままの意味ですがルータを識別するものです。
では、本設問の構成の中でルータは存在するでしょうか?
図3のネットワーク構成図を掲載します。
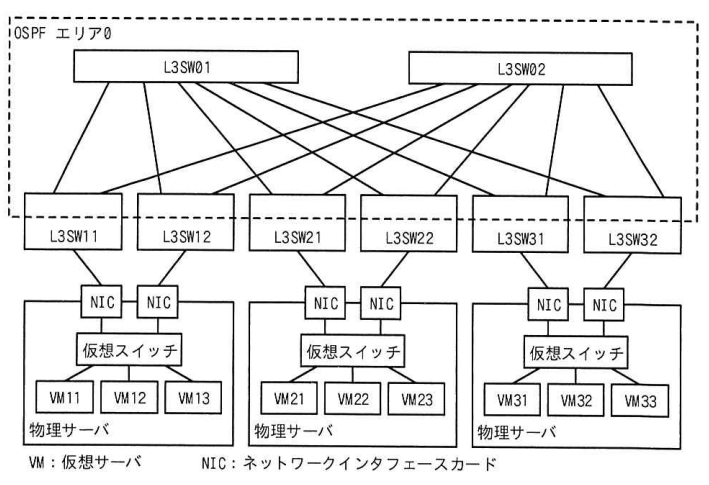
構成図を見てもルータは存在しませんが、OSPFが稼働している範囲が記載されています。
つまり、ルータIDとはL3SWを識別する情報となります。
解答例は「L3SW」という単語を入れて以下のようになります。
OSPFが動作する各L3SW(14字)
(3)
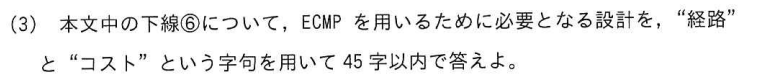
下線⑥は以下の通り記述されています。
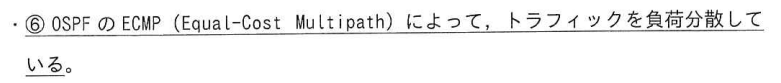
OSPFのECMP(Equal-Cost Multipath)の設計について問われています。
OSPFにおけるECMPの説明を記載します。
これらの説明文より、”経路”と”コスト”という字句を用いて以下のような解答例となります。
複数ある経路のそれぞれの経路について、コストの合計値を同じ値にする。(34字)
(4)
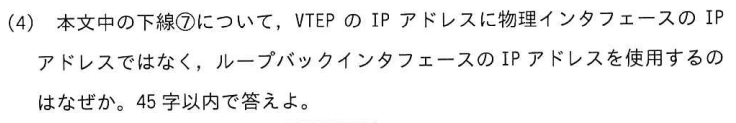
下線⑦の記述を見てみましょう。
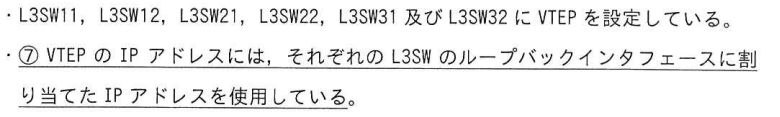
この設問はループバックインタフェースの一般的なメリットを考えることで解答ができると思います。
ループバックインタフェースはルータやL3SWの内部に仮想的に作成される論理インタフェースです。
物理的なポートに依存しないため、常にリンクアップした状態を維持できます。
よって解答例は以下の通りです。
一つの物理インタフェースに障害があってもVTEPとして動作できるから(34字)
ちなみに、筆者は以下のように回答しました。
物理インタフェースがダウンしてもL3SWが稼働していれば通信が行えるため(36字)
(5)
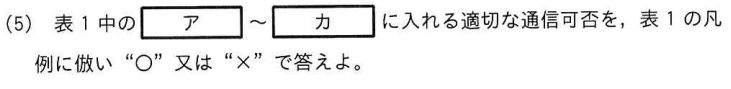
まずは表1を見てみましょう。
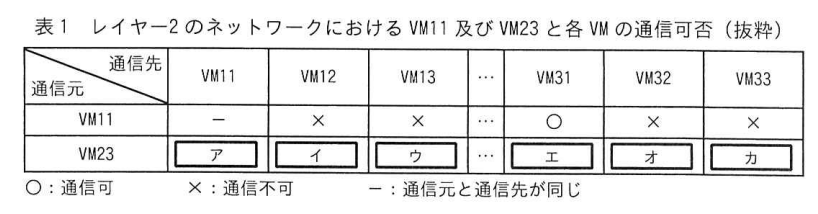
特定のVMについて、他のVMと通信が可能かどうかを問われています。
本設問はVM23に着目していますが、上段のVM11の通信可否がかなりのヒントになっています。
図4の構成図を掲載します。
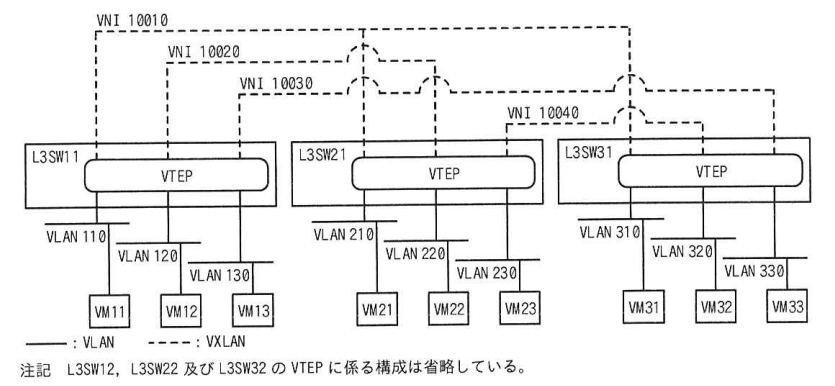
この構成図にVM11の経路を書き込んでみました。
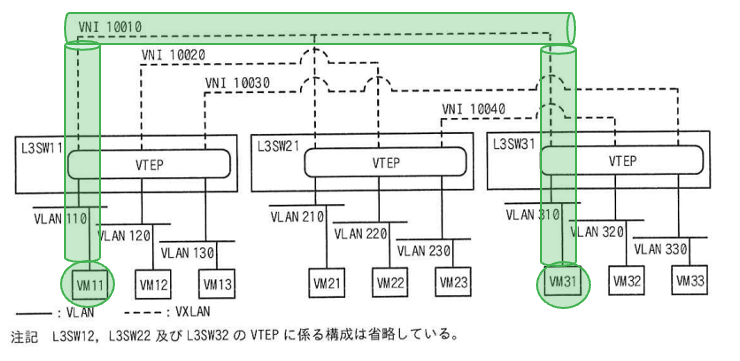
VM11は同じVXLAN(VNI=10010)に所属するVM31と通信が可能です。
※VM11は同様のVXLANに所属するVM21とも通信が可能なはずです。
これらを踏まえて、VM23の経路を書き込んでみました。
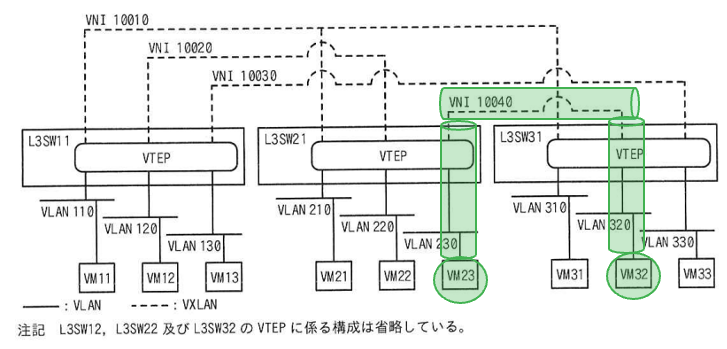
この図から明らかな通り、VM23は同じVXLAN(VNI=10040)に所属するVM32と通信が可能です。
よって、正解は以下の通りです。
(ア)×
(イ)×
(ウ)×
(エ)×
(オ)○
(カ)×
表に書き込むとこのようになります。
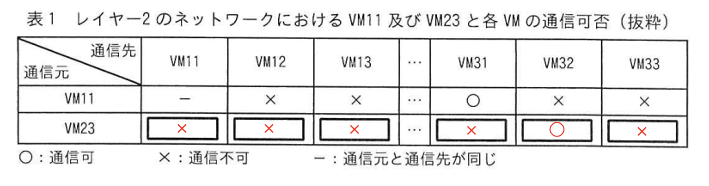
次回へ続く
いかがだったでしょうか?
さすが午後Ⅱ試験、解説が非常に長くなってしまいました。
まだまだ書き足りない気持ちでいっぱいですが…
一旦ここで終了とさせていただき、続きは次回の記事で書いていきます。
なるべく早めに投稿できるよう頑張りますので、お待ちいただけますと幸いです。
それではまた次回の記事で!
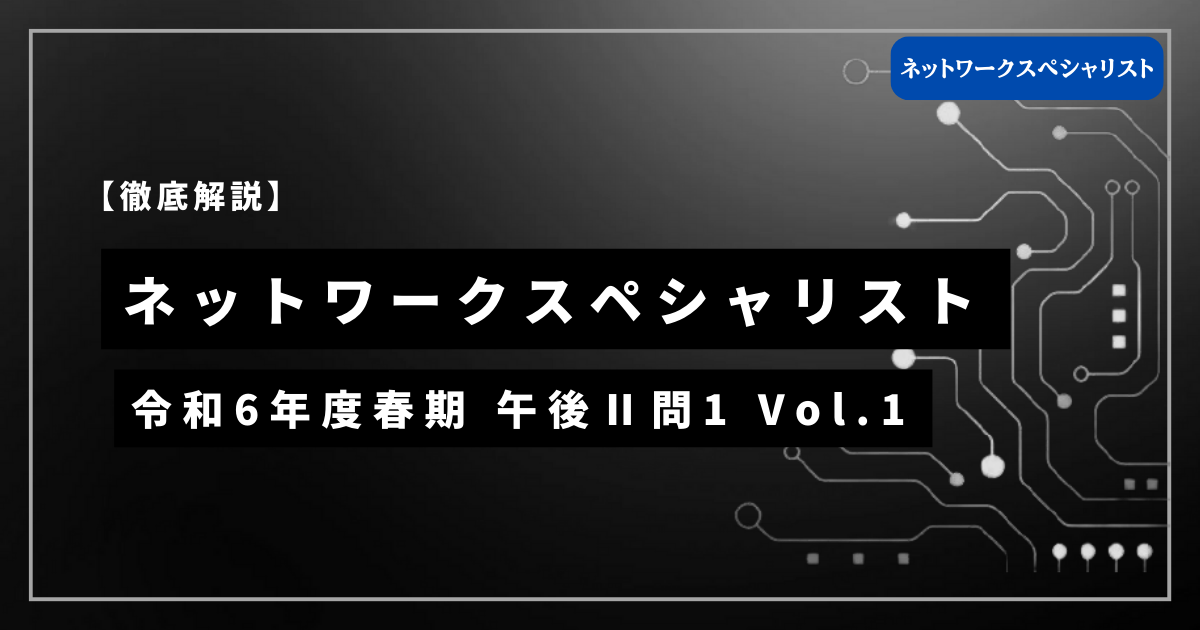



コメント